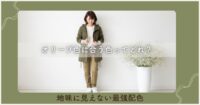冬の定番アウターとして知られる「ダッフルコート」。 フードやループ、トグルがアクセントになっていておしゃれですよね。
でも 「そもそもダッフルコートってどんなコート?」 「ピーコートと何が違うの?」 「学生っぽいイメージがあるけど、大人が着るとダサいかな?」 「何歳くらいまで着ていいもの?」 といった疑問も…。
この記事では、そんなダッフルコートに関するあらゆる疑問を解決します。 ダッフルコートの基本的な知識や歴史から、多くの人が気になるネガティブなイメージの真相、そして今日から真似できるおしゃれな着こなしのコツまで、分かりやすく解説します。
そもそもダッフルコートとは?『基本のき』を解説

まずはじめに、ダッフルコートがどのようなアウターなのか、その定義と特徴的なデザインについて解説します。これさえ押さえれば、ダッフルコートの基本は完璧です。
ダッフルコートの定義と最大の特徴
ダッフルコートとは、一般的に「厚手の起毛ウール生地(メルトンなど)で作られたフード付きのコート」を指します。
そして、他のどのコートにもない最大の特徴が、フロント部分のデザインです。一般的なボタンではなく、「トグル」と呼ばれる浮き型の留め具を、麻紐や革製のループに引っ掛けて前を閉じます。このユニークなデザインこそが、ダッフルコートの象徴と言えるでしょう。
各部の名称とデザインの意味
ダッフルコートの個性的なデザインには、一つひとつに実用的な意味が込められています。
- トグルとループ
水牛の角や木材で作られることが多い「トグル」は、厚手の手袋をしたままでもコートの着脱がしやすいように工夫されたものです。その機能的なデザインが、今ではファッションのアクセントになっています。 - フード
もともとは、船乗りたちが帽子の上からでも被れるように大きく作られていました。雨風や寒さから頭部を守るための実用的なディテールです。 - ショルダーパッチ(ストームパッチ)
肩部分に付けられた当て布のこと。肩を補強し、雨水の侵入を防ぐ役割があります。デザイン上のアクセントとしても機能しています。 - 大きなパッチポケット
コートの外側に縫い付けられた大きなポケット。道具などを気軽に入れられるように設計された、実用性の高いデザインです。
ダッフルコートの起源と歴史

今ではファッションアイテムとして人気のダッフルコートですが、そのルーツは意外な場所にありました。歴史を知ることで、より一層このコートに愛着が湧くはずです。
その起源は、北欧の漁師たちが着ていた仕事着に遡ります。厳しい寒さや荒波から身を守るための、非常に丈夫で機能的な作業服でした。
このコートに注目したのが、第二次世界大戦中のイギリス海軍です。その優れた防寒性と機能性から、海軍兵士の公式な防寒着として採用されました。極寒の海上で任務にあたる兵士たちにとって、ダッフルコートは命を守るための重要な装備だったのです。
戦後、軍で使われていた大量のダッフルコートが市場に放出されると、その質の高さとファッション性から一般の人々の間でも人気を博し、冬のカジュアルウェアとして世界中に広まっていきました。
【比較表】ダッフルコートとピーコート(Pコート)の決定的な違い

冬の定番コートとしてよく比較される「ダッフルコート」と「ピーコート」。どちらも海軍にルーツを持つミリタリーウェアですが、デザインや印象は全く異なります。両者の違いを表で分かりやすく整理しました。
| 特徴 | ダッフルコート | ピーコート |
|---|---|---|
| フロント | トグルと麻紐ループ | ダブルボタン |
| フード | あり | なし(大きな襟が特徴) |
| 起源 | 漁師の仕事着、イギリス海軍 | オランダ海軍、イギリス海軍 |
| 全体の印象 | カジュアル、可愛らしい | きれいめ、トラッド |
このように、フードの有無やフロントデザインが大きな違いです。カジュアルで少し柔らかな印象を与えたいならダッフルコート、よりシックで大人っぽい印象にしたいならピーコートがおすすめです。
みんなの疑問に答えます!ダッフルコートは「ダサい」「重い」「何歳まで」?

購入をためらう原因になりがちな、ダッフルコートのネガティブなイメージ。ここでは、それらの疑問に正直にお答えし、解決策を提案します。
疑問1. ダッフルコートはダサい?子供っぽい?
結論から言うと、着こなし方次第で非常におしゃれに見えます。
「ダサい」「子供っぽい」というイメージは、日本の多くの学校で制服のコートとして採用されてきた歴史が影響していると考えられます。しかし、それはダッフルコートが持つ普遍的なデザイン性の裏返しでもあります。
解決策は「選び方」。
- 色ネイビー、ブラック、キャメル、グレーといった落ち着いた定番色を選ぶ
- サイズ感体にフィットしすぎない、程よくゆとりのあるサイズを選ぶ
- 素材感上質なウール素材など、高級感のある生地を選ぶ
この3点を意識するだけで、学生っぽさを払拭した洗練された大人の着こなしが可能に!
疑問2. ダッフルコートは”重い”って本当?
伝統的な製法のものは重い傾向にあります。
これは、防寒性・防風性を高めるために、高密度に織られた厚手のウール生地(メルトン)を使用しているためです。
しかし、これも過去の話になりつつあります。近年はファッションブランドの努力により、ウールの質感を保ちつつも驚くほど軽量な素材が開発されています。 購入時に素材や重さをチェックすれば、快適に着られる一着がきっと見つかりますよ。
疑問3. 結局、ダッフルコートは何歳まで着られる?
結論は「何歳でもOK」です。年齢制限は一切ありません。
ダッフルコートは、流行り廃りのない完成されたデザインを持つアウターです。年齢に合わせて着こなしをアップデートすれば、生涯にわたって愛用できます。
- 20代発色の良いニットやパーカーと合わせ、フレッシュでカジュアルな着こなしを楽しむ
- 30代・40代以降上質なニットやスラックスと合わせ、上品な大人カジュアルを演出
明日から使える!ダッフルコートのおしゃれな着こなしコーデ術【レディース】
基本的な知識を押さえたところで、実践的なコーディネートをご紹介します。写真付きで分かりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
ダッフルコートのきれいめコーデ

ネイビーやキャメルのロングダッフルに、センタープレスの入った白やグレーのパンツを合わせるスタイル。インナーにシンプルなニットを合わせれば、洗練された大人コーデが完成します。
ダッフルコートのスタイルアップコーデ

目線が上がるショート丈のダッフルコートは、プリーツスカートやフレアスカートと相性抜群。全体のバランスが取りやすく、スタイルアップ効果が期待できます。
ダッフルコートの上品フェミニンコーデ

色数を抑えてまとめることで、カジュアルなダッフルコートも一気に上品で女性らしい印象に。冬の街に映える、柔らかなスタイリングです。
失敗しない!自分にぴったりのダッフルコートの選び方

長く愛用できる一着を見つけるための、4つのチェックポイントをご紹介します。
着丈で選ぶ(ショート/ミドル/ロング)
- ショート:軽快でアクティブな印象。スカートやワイドパンツと好相性。
- ミドル:最もベーシックで着回しやすい長さ。お尻が隠れる丈感。
- ロング:大人っぽく上品な印象。防寒性も高く、きれいめコーデに最適。
色で選ぶ(定番色/トレンド色)
初めての一着なら、ネイビー、キャメル、グレー、ブラックなどの定番色が着回しやすくおすすめです。2着目以降であれば、ホワイトやグリーンといったトレンドカラーに挑戦するのも良いでしょう。
素材で選ぶ(ウール/ポリエステルなど)
防寒性を重視するならウール100%が理想的。軽さや手入れのしやすさを求めるなら、ウールと化学繊維の混紡素材も良い選択肢です。実際に触れて、生地の厚みや肌触りを確認しましょう。
サイズ感で選ぶ
インナーに厚手のニットやジャケットを着込むことを想定し、肩周りや腕周りに少しゆとりのあるサイズを選ぶのがおすすめです。試着の際は、実際に冬に着る服装で行うと失敗がありません。
まとめ
この記事では、ダッフルコートの基本的な知識から、よくある疑問、おしゃれな着こなし方までを網羅的に解説しました。
- ダッフルコートは、漁師や海軍の服をルーツに持つ、歴史と機能性を兼ね備えたアウター。
- 「ダサい」「何歳まで」といった不安は、色やサイズの選び方、コーディネート次第で解消できる。
- ピーコートとの違いを理解し、自分のスタイルに合った一着を選ぶことが重要。
ポイントを押さえれば、ダッフルコートは冬のファッションを格上げしてくれる心強い味方になります。ぜひこの記事を参考に、あなただけの一着を見つけて、冬のおしゃれを楽しんでください。