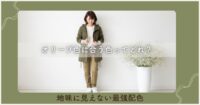首元をすっきりと見せてくれるスタンドカラー。
洗練された印象を与えるこの襟型は、実は700年以上の長い歴史を持っています。
軍服や労働着から始まり、現代のファッションアイテムとして愛される存在へと変化してきました。
本記事では、スタンドカラーの起源から現代に至るまでの変遷を、詳しくご紹介します。
スタンドカラーとは 襟羽のない立ち襟デザインの総称

スタンドカラーとは、折り返しのない立った襟の総称を指します。
正式には「スタンディングカラー」や「スタンドアップカラー」とも呼ばれています。
襟が首に沿って立ち上がるデザインが特徴で、襟を折り返さない分、首元がすっきりとした印象になるのです。
スタンドカラーにはさまざまなバリエーションが存在します。
- 中国服に見られるマオカラー
- 学生服の詰襟
- バンドカラー
- チョーカーカラー
- マンダリンカラー
一般的なシャツと異なり、スタンドカラーのアイテムはノーネクタイで着用します。
そのため、カジュアルな印象を与えながらも、洗練された雰囲気を演出できるのが魅力といえるでしょう。
スタンドカラーの起源は19世紀の軍服と労働着

スタンドカラーの起源には複数の説がありますが、もっとも古いものは14世紀にまで遡ります。
1300年代のフランス・ノルマン地方の貴族が、寒さをしのぐため、そして衣服の補強のために考案したバンドカラーが源流とされています。
さらに古くは、北アジアの遊牧民や騎馬民族の衣服に立襟が広く使われていました。
頸部の保護や保温、そして刃物や弓矢からの防御という実用的な機能を持っていたのです。
立襟の軍服に由来する機能性と威厳
スタンドカラーが世界中に広まったきっかけは、19世紀の軍服への採用でした。
英国陸軍や米海軍の制服に立襟が取り入れられ、首の温度を保ちつつ攻撃から守る機能が評価されました。
清朝中国の官僚(マンダリン)が着用していたことから、欧米では「マンダリンカラー」という名称も定着しています。
立襟の軍服は威厳と規律を象徴するデザインとして、世界各国の軍隊に採用されていきました。
日本でも明治時代に軍服とともに立襟が導入され、「ハイカラ」という言葉の語源になったとも言われています。
学生服の詰襟も、この時代の軍服が元になったデザインです。
付け襟が源流のデタッチャブルカラーシャツ
19世紀のシャツの歴史において、カラーとカフスが取り外し可能だった時代がありました。
これが「デタッチャブルカラー」と呼ばれるスタイルです。
スタンドカラーシャツは、本来であれば仕事を終えてカラーを外し、くつろいでいるときの格好でした。
当時は洗濯が大変だったため、汚れやすい襟とカフスだけを取り外して洗えるよう工夫されていたのです。
戦前の日本では、白いスタンドカラーシャツの上に着物を着て袴をつける「書生風」という着方が流行しました。
ファッションアイテムとしてのスタンドカラーの歴史

実用的な機能から生まれたスタンドカラーは、20世紀に入るとファッションアイテムとして進化していきます。
軍服や労働着という枠を超え、カジュアルウェアやデザイナーズファッションとして再解釈されてきました。
ここでは、ファッション史におけるスタンドカラーの重要な転換点を見ていきましょう。
20世紀初頭 カジュアルウェアへの進化
20世紀初頭、服飾の世界では大きな変化が起こりました。
19世紀に流行した極端に高い立ち襟から、より実用的で常識的な高さへと変化していったのです。
1850年頃には「グラッドストンカラー」という立ち襟が流行し、1854年頃には顔が半分隠れるほどの高い「オールラウンドカラー」が登場しました。
しかし世紀末になると、襟の高さは3インチ程度の常識的なものに落ち着きます。
この時期に、スタンドカラーやドッグカラー、シェイクスピアカラーなど、さまざまなカラースタイルが生まれました。
軍服や作業着としてだけでなく、カジュアルウェアとしてのスタンドカラーが定着していったのです。
1960年代 ビートルズが流行させたマオカラージャケット
1960年代は、スタンドカラーがポップカルチャーと結びついた重要な時期です。
特に、モッズファッションの流行とともに、スタンドカラーのジャケットが若者の間で人気を博しました。
ビートルズをはじめとする当時のアーティストたちが、マオカラー(襟腰の低いスタンドカラー)のジャケットを着用したことで、一気にトレンドとなりました。
中国の人民服に由来するマオカラーは、従来のフォーマルな印象とは異なり、カジュアルでモダンな雰囲気を演出します。
1960年代のイギリスでは、ファッションと音楽を愛する若者たちの間で、スタンドカラーが新しいスタイルの象徴となったのです。
1980年代以降 デザイナーズブランドによる再解釈
1980年代、日本のデザイナーによってスタンドカラーは新たな進化を遂げます。
三宅一生がコレクションでスタンドカラーシャツを発表したことが、日本での流行のきっかけとなりました。
ノーネクタイでありながらドレッシーさを保つオシャレなスタイルとして、知的な職種の人々に支持されていきます。
デザイナーたちは、スタンドカラーの持つミニマルな美しさと機能性に注目しました。
シンプルながらも存在感のあるデザインは、モダンでアーティスティックな表現として再解釈されていったのです。
1980年代以降、スタンドカラーはカジュアルからフォーマルまで、幅広いシーンで活用する定番アイテムとなりました。
アイテム別にみるスタンドカラーのルーツ

スタンドカラーは、シャツ、ジャケット、コートなど、様々なアイテムに取り入れられています。
それぞれのアイテムには独自の歴史と発展の経緯があり、現代のファッションに受け継がれています。
ここでは、代表的な3つのアイテムについて、そのルーツを詳しく見ていきましょう。
スタンドカラーシャツの歴史
スタンドカラーシャツの歴史は、19世紀のデタッチャブルカラーに始まります。
当時、カラーとカフスは取り外し可能で、スタンドカラーシャツは仕事後のくつろぎ着として着用されていました。
日本では戦前、「書生風」と呼ばれる着方が流行し、白いスタンドカラーシャツの上に着物と袴を合わせていました。
1980年代に三宅一生がコレクションで発表したことで、ファッションアイテムとしての地位を確立します。
現代では、ノーネクタイで着られる洗練されたシャツとして定番化しています。
カジュアルからビジネスカジュアルまで、幅広いシーンで活躍するアイテムとなっています。
スタンドカラージャケットの歴史
スタンドカラージャケットは、軍服のデザインが民間に広がったことが起源です。
19世紀の軍服では、立襟が威厳と規律を象徴するデザインとして採用されていました。
1960年代には、マオカラージャケットとして若者文化の中で再評価されます。
ビートルズなどのアーティストが着用したことで、モダンでスタイリッシュなアイテムとして注目を集めました。
1980年代以降は、デザイナーズブランドによって様々なバリエーションが生まれています。
シャープで洗練された印象を与えるスタンドカラージャケットは、現代でも人気の高いアイテムです。
スタンドカラーコートの歴史
スタンドカラーコートの起源は、ビクトリア朝時代の男性用服にまで遡ります。
19世紀のイギリスでは、襟の高さや形状がファッションの重要なポイントとされていました。
立ち上がった襟は社会的地位を示す要素として、貴族や上流階級の男性に好まれたのです。
初期のスタンドカラーコートは、ウールやカシミヤといった高級素材で作られていました。
装飾的なステッチやボタンが施され、贅沢な印象を与えるデザインが特徴でした。
現代では、首元を覆う襟元のデザインが防寒性と美しさを兼ね備えたアイテムとして人気を集めています。
まとめ
スタンドカラーは、14世紀のフランスや北アジアの遊牧民族の衣服をルーツに持つ、700年以上の歴史を持つ襟型です。
19世紀には軍服や労働着として機能性を重視されながら広まり、20世紀に入るとカジュアルウェアとして進化しました。
1960年代にはビートルズらによってポップカルチャーの象徴となり、1980年代には三宅一生などのデザイナーによって再解釈されました。
現代では、シャツ、ジャケット、コートなど様々なアイテムに取り入れられ、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍しています。
首元をすっきりと見せながら洗練された印象を与えるスタンドカラーは、時代を超えて愛され続けるデザインなのです。